こんにちは。雇われ税理士のマッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算方法」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「配偶者控除」についてです。
所得控除「配偶者控除」とは・・
配偶者とは、夫からみたら妻、妻からみたら夫のことをいいます。
あなたが奥さんまたは旦那さんを養っていたとします。
養っていたとするならばその分だけ最低生活費が発生するわけですね。
独身よりは・・・。
そこで税率を乗じる前の課税対象所得金額の計算の際、あなたのもうけを表す給与所得金額から※一定の金額を控除する訳です。
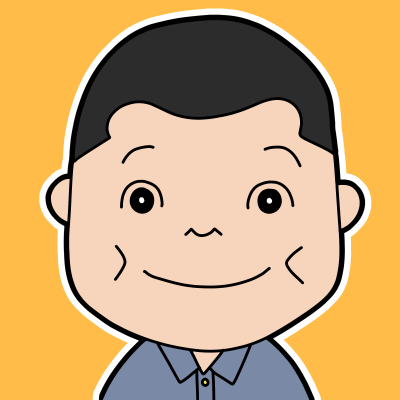
※一定の金額とは次の通りです。(2020年~)
| その年の所得金額が | 配偶者控除の金額 |
|---|---|
| 900万円以下 (所得が給与のみなら年収1095万円以下) | 38万円[48万円] |
| 900万円超950万円以下 (所得が給与のみなら年収1095万円超1145万円以下) | 26万円[32万円] |
| 950万円超1000万円以下 (所得が給与のみなら年収1145万円超1195万円以下) | 13万円[16万円] |
| 1000万円超 (所得が給与のみなら年収1195万円超) | 0円[0円] |
| [ ]の金額は配偶者の年齢が70歳以上(その年12/31現在)の場合 |
「配偶者控除」を受けるための「配偶者」の要件
上記「所得控除・・配偶者控除とは」において、「養っていたとするならば~」とありました。
それでは配偶者に「稼ぎ(もうけ=所得)」があったとしたら、どうなるのでしょう?
配偶者が働いていて稼ぎもあるならば、その配偶者自身のお給料において最低生活費を考慮した「基礎控除」を受けています。
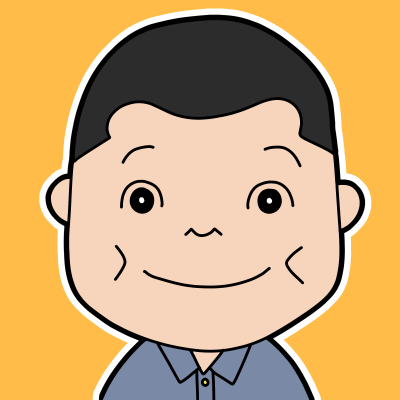
「配偶者控除」の適用を受けるためには、配偶者について要件があります。
その要件とは次の通りです。
- 配偶者であること
- 生計を一にしていること
- 配偶者の所得金額が48万円以下であること
①配偶者であること
配偶者でなければ「配偶者控除」は受けられません。
あたりまえですね。
「配偶者」は民法上の配偶者をいいますので、内縁の妻・夫は対象外となります。
②生計を一にしていること
同じサイフで生活しているということです。
経済単位が一ということですから、必ずしも同居を要件としていません。
単身赴任しているがお金を常に送金しているなども、「生計一」となります。
③配偶者の所得金額が48万円以下であること
配偶者に稼ぎがあるならば「配偶者控除」の適用はありませんということでした。
配偶者の所得が48万円以下ならば、生活費も稼げていないということです。
配偶者を扶養する必要がありますね。
ちなみに所得が給与のみならば、年収103万円以下で所得48万円以下となります。
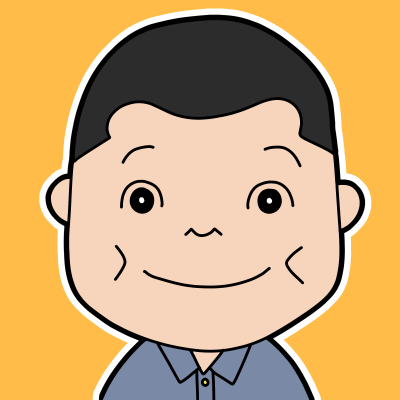
3つ目の要件「配偶者の所得が48万円以下」すなわち給与年収103万円ライン。
「配偶者の給与収入が年103万円を超えたら、ただちに控除される金額がなくなるの?」
そういう訳ではありません。
「配偶者特別控除」という所得控除によって、配偶者の年収によりただちに控除金額が0円にならないように控除金額のバランスをとっています。
最後に
「配偶者控除」
今は共働きの方も多いと思うので、共働き夫婦の方は適用がないと思います。
ワタシ事ですが、ワタシの妻はいわゆる「非正規」として働いています。
収入が不安定のため、ワタシ自身の所得税の計算において「配偶者控除」の適用がある年とない年があります。
この「配偶者控除」の適用を受けるときは、なんだか「カミさん背負っているんだな~」とか「がんばらなきゃな~!」とか感じます。
世代の考え方の違いもあると思うので、意見はあると思いますが、「配偶者控除」の適用を受けると、ちょっぴりうれしいマッキーでした。

